9月例会 9/18(土) 19:00~22:00
テーマ
・新学習指導要領における「国語科の見方・考え方」について(予定)
講師 茅野政徳先生
山梨大学 大学院総合研究部教育学域 教育実践創成講座教職大学院)
(元 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 研究主任)
2021.8.28 感想(抜粋)
講演直後から,本会のグループラインに書き込みが殺到しました。
大人でも,子どもでも「書きたい!」という感動があれば,誰に言われなくても
書くものだということが再認識できました。
素晴らしい講演でした!!
・本日は貴重な場を設定していただきありがとうございました。「言葉に立ち
止まる」子らを育てていくためには、まずは自分自身が言葉に立ち止まれる
感覚をもたないといけないし、この年になると若い先生たちにもそういう力を
付けられるようにならなければと強く感じました。昨日の授業(昨日までの
授業)から掲示物やノートの在り方まで、反省することがたくさん・・・
まずは「少年探偵ブラウン」を買ってみます。ちなみに、茅野先生が関わって
おられる「指導と評価を一体化する 小学校国語実践事例集」という本に、
今日の大造じいさんとガンなどの具体的な授業中の様子が載っていました。
ぜひ読んでみてくださいと勝手に宣伝しておきます。
・今日は素敵なお話を聴く機会を設けてくださり、ありがとうございました。
教科書を、言葉を自覚的に読み直してみようと思います。まずは、自分自身が
語彙を増やし、子どもたちと一緒に言葉に立ち止まって考えていきたいです。
それを一緒に楽しんで考えられたら、子どもたちも言葉を大切にしたり、ん?
と考えられたりできるのだろうなと感じました。昔話の読み聞かせもたくさん
していこうと思いました。週明け子どもたちと授業をするのが楽しみです。
茅野先生、そして繋いでくださった足立先生、本当にありがとうございました。
・あすなろ会の勉強会は毎回凄く勉強になって楽しくて、あっという間に時間が
過ぎてしまいますが、今回は特に時間が過ぎるのが早く感じました。「言葉に
立ち止まる」「言葉に自覚的になる」「言葉は人が生み出すもので、自分自身
を変えるもの」という茅野先生のキーワードをこれからの教員生活で意識しな
がら国語科の授業に取り組みたいと思います。今ちょうど「ごんぎつね」の授業
をしているので、茅野先生の話を聞かせていただきながら教科書をパラパラと
めくり、来週の授業で子どもたちにどの言葉で立ち止まらせようか、どの言葉で
立ち止まってくれるかなと考えていると、凄く楽しい気持ちになりました。
オノマトペの話の最中では、留学していた時のことを思い出しました。留学先で
日本語を勉強していたニュージーランドの学生が「日本語には色々なオノマトペ
がありすぎて何が何だか本当に分からない。でもそこが日本の良さで楽しいとこ
ろだ。」と言っていました。何気なく自分たちの身の回りにある言葉でも、これ
からは自分自身も子どもたちも立ち止まって意識しながら学んでいきたいと思い
ました。うまく文章にまとまっていないかもしれませんが、とても充実した勉強
会になりました。ありがとうございました。まだまだ茅野先生からお話をお聞き
したかったです。
・今回も貴重な場を設定していただき,ありがとうございました。今回のお話を
聞かせていただく中で,言葉に立ち止まるってどういうことなのか,言葉に
自覚的になるとはどいうことなのかを学ぶことができました。「どうぶつ園の
じゅうい」の学習のお話をされたときに,自分が言葉に立ち止まれていなかった
ことに気付かされました。また分厚いノートについてのお話も聞くことができ,
さらに本物の茅野先生のノートを見てみたいなと感じました。そのお話の中で,
「子どもたちから学ばせてもらったことです」というお話がありました。僕が
いつもお話をまたお聞きしたいなと思う先生方は,子どもたちから学ばせて
もらっているという考え方をされているように感じます。国語の見方考え方を
働かせるとはどういったことなのかということを学ぶと共に,子どもから学ぶ
という姿勢が教師として成長する大切な軸だと再確認しました。
・今日は貴重なお話を聞く機会を与えて頂き、ありがとうございました。これまで
子どもに登場人物どんな気持ちだろうと簡単に聞いていたなと思いました。音読
もみんなでどうやって読むのがいいのかな?と色々な読み方で読んでいこうと
思いました。また、語彙を増やせるように分からなかった言葉などをみんなで
調べ、掲示していこうと思います。
・今回はありがとうございました。茅野先生の授業を見て、今学習している一年
国語科の「やくそく」という授業を思い出しました。物語の終末、くんねり
くんねりという言葉に子どもたちは立ち止まったのですが、私はそこでくんねり
くんねりってどういう感じかなあ?と投げかけました。そこで1人の男の子が
席から立ち出して歩いてみる演技。私はそこでなるほど、そんな感じか〜としか
言えませんでした。もっと他の人はどう思う?と聞いたり、くんねりくんねりに
合う言葉はある?と尋ねたりできたのではないかと、茅野先生のお話を聞いて
思いました。言葉に立ち止まる授業、連休明けから実践していきたいと思います。
10月、11月もこれからよろしくお願いします。
・今日は貴重な時間をいただき、本当に有難い時間を過ごすことができました。
授業だけでなく、我々大人へのお話も、興味深く面白いものばかりで、ただただ
感激しています。
「言葉に立ち止まる」
子どもたちに求めたいことですが、まずは自分自身が出来るようにならなければ
と身が引き締まる思いで聞かせていただきました。
「言葉に自覚的になる」
恥ずかしながら私も語彙は豊かでない方なので、私生活で困った時には「やばい」
「すごい」などの言葉に頼ってしまう傾向があり…大人になった今、後悔している
ところです。自分のクラスの子どもたちはそうならないように、スポンジのように
何でも吸収するこの時期だからこそ、たくさん語彙を増やしてあげたいです。
これからも子どもたちと共に勉強したいと思います。
・今日も充実した勉強会でしたね。茅野先生のお話をこんなにじっくり聞けることは
そう無いと思うのでとても幸せな時間でした。国語科の見方考え方は他の教科以上に
具体が見えにくく、今日のスライドの初めに茅野先生が仰っていたことと同じことを
感じていました。
働かせるためのキーワードは「言葉に立ち止まる」でしたね。言うのは簡単ですが、
言葉に立ち止まれるようになるのも、子どもを言葉に立ち止まれるように育てるのも
ステップが必要で、目の前の子の実態に合わせて育てるのは簡単ではないと感じて
います。私はこれからごんぎつねの教材に入ります。今日の学びを生かして、単元を
デザインしてみたいと思います。「言畑を耕そう」という言葉の意味が更新され、
さらに涵養していく感じがしました。
・あの後テレビで三省堂の辞書が8年ぶりに再編集されることが話題になっていました。
8年前も再編集のニュースで辞書を買ったことを思い出しました。再編集は、新しい
言葉を足す、使わない言葉を引く、今の時代に合わせて言葉の意味を変える作業だと
言われていました。言葉の意味も変えるのか…と驚きました。そこで「言葉は進化も
退化もする」という昨夜のお話を思い出しました。改めて言葉の大切さに気付きまし
た。伝えるための言葉です。伝えたいと思うことを子どもたちに増やしていきたいで
す。今回の辞書には、「もふもふ」が入っているのかな…

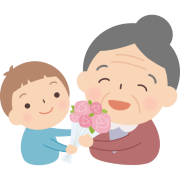


コメント