10月例会 10/16(土) 19:00~22:00
テーマ
・新学習指導要領における「生活科の見方・考え方」について講師 外舘 ゆき子先生
三浦市立旭小学校 教頭
(元 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 研究主任)
今回の講演で再確認できたのは,私たち教師の仕事は「子どもをどう見取るか」,
そしてその中で教師と子どもとの「ズレ」をどう感じ,それをどう子どもの学びに
返したらよいかということです。そのためには,子どもの行動やつぶやきを丁寧に
見聞きしたり,プリントのコメントの工夫をしたりすることで,子どもの思いや願い
を教師が的確に受け止めていく必要がありますね。感銘を受けた講演でした。
また今回も横小OB,OGの先生方をはじめ,たくさんの先生方に参加していただき
ました。この場を借りて,お礼を申し上げます。
以下,参加者からのコメントです。
・今回もたくさんの先生方とつないでいただきありがとうございました。生活・総合を
核として,「自分事の学び」を積み重ね「言うことを聞かない子」を育てていく学校
づくりが今の課題だと改めて感じました。自分自身もまだまだ自分の思い描くレール
に乗せてしまっていることがあります。子どもの見取りも浅いです。あえて失敗させる
くらいの余裕をもって子どもたちと向き合っていきたいと改めて思いました。
・お話を聞きながら、生活科の学習をしていたときのことを思い出していましたが、
活動のための活動になっていた(意図や目的のための活動になっていない)のではない
かと反省だらけでした。ねらいをこちらがしっかりともっておくことで、学びの
深まりにつながるし、子どもの思いをどう価値づけしていくかの指針になっていく
のだと、理解が深まりました。思い返せば学んできたことばかりだと反省です。でも、
今回また参加できたことでこうやって気付くことができ、感謝です。ありがとうござ
いました。
・このあいだ公園に行ったとき、他の親子の会話(といっても、子どもさんの声しか
聞き取れませんでしたが…)が聞こえてきました。小学生か年長さんかそらくらい
かなと思いますが、
「木って生きてるん?」
「なんで木は動いてへんのに生きてるん?」
「じゃあ石も生きてるん?」
おそらく、自分がよく知っている生き物は動いているということなのかな、と思った
のですが、わたしならどう返すかな〜と考えていました。「なんでかな」と言うかな
と思ったのですが、「なぜそう思ったん?」というと、子どもの思いが引き出せそう
だな、他にも生き物について広がっていきそうかな?!なんて考えました。普段,
我が子とかかわる中でも、どう問い返すかは大切だなと思うので、考えられる環境を
作っていきたいと思いました。
・今日の勉強会に参加させていただいて,どのように子どもたちを見取っていくのか
とてもわかりやすく教えていただきました。自分自身の見取り方が甘いのもあります
が,私も子どもたちを見取る中でズレが大きいなと感じていました。今回のお話の
中でそのズレを感じどうすれば良いのかを考えることが大切だと学ぶことができ
救われたように感じます。そのズレをどう小さくしていけるのかをこれからも問い
続けていきたいと思います。また,自分の学級経営をふりかえって低学年のうちから
自分で決める場をもっともっと設定していく必要があるなと感じました。自分たちで
決めて試行錯誤する場を無くさないよう気を付けていきます。
・外舘先生のお話をお聞きし、私も授業でどうしてそう思ったの?と聞けているか
考えていました。今、いきものとなかよしの学習をしています。子どもたちが
生き物となかよしになる環境があるので、その場所を用いて、どんな生き物を
育てたいか子どもたちと一緒に考えました。中には、うさぎやにわとりを飼いたい
と言った子どももいたのですが、私が勤務する学校には小動物がいません。
メダカという子どもがいたので地域の方にお願いをして、魚を育てることになり
ました。動物を飼う環境も今の状況で、どこまでできるかを考えるととても限られ
ているなと思います。そんな中でも、どうやって育てるのか、またえさはどうする
のか子どもたちと一緒に考えていきたいと思いました。子どもたちの思いを大切に、
これからも生活科の学習を楽しみたいと思います。
・今回も、外館先生をはじめたくさんの先生方とご一緒に学ぶことができてありがた
かったです。ワークシート一つにしても、いろいろな書き方があることを知り、
次はどんなものにしようかと考えるとワクワクしてきました。子どもの思考を促す
コメント(朱書)も意識したいです。また、いい意味で「言うことを聞かない子」
を育てていく学級経営についても大変興味をもちました。1年生だから…と教師が
レールを敷くのではなく、1年生のうちから自分の考えをしっかりもてる子を育てて
いかなくてはいけないんだな、と反省していました。明日から、自分で考える力を
培うことを意識していきたいと思います。
・振り返りカード(おもったこと、気づいたことを書いてみよう)を書かせて満足を
していたところもあるので、振り返りカードも見直さないといけないなと感じ
ました。また、どうしてそう思ったの?どうして?なんでと聞くことで子ども
たちの学びが深くなることを知りました。私の学校は動物は飼っていませんが
(昔はいたそうですが)各クラスにメダカがいます。子どもたちは愛着をもって、
名前をつけたり餌をあげたり、水槽を自ら綺麗にしたりしようとしています。
また機会を捉えて,この子どもたちの行動を認めてあげていこうと思います。
今回もたくさんの学びをありがとうございました。
外舘先生からも温かいコメントをいただきました。
・足立先生がお話ししてくださった「H君」。中学1年生になりました。今回、その
エピソードを紹介しようと思い、パワポに使う写真を探したのですが、私も持って
おらず、横小に問い合わせてみたところ、サーバーに不具合が起き、過去のデータ
が取り出せなくなってしまったとのこと。残念ながら入手できませんでした。
朝から「足立先生はどこ?」と探しまくっていた子どもたち、授業中にたくさんの
参観者をかき分けて飛行機を飛ばすスペースを作った女の子たち、思うように飛ば
なかった紙飛行機、H君の涙…。お話を聞きながら、いろいろなことを懐かしく
思い出しました。
足立先生の元で勉強されている皆さんは、熱心だし、質問の内容もいいですね。
日頃から、子どものこと、授業のこと、学校のこと…色々と考え悩みながら、現場に
立たれていることが伝わってきました。私も、授業をしなくなった今も「子どもに
育ててもらっている」ということに変わりありません。これからも皆さんと一緒に
学ばせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。


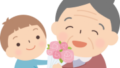

コメント