1月例会 1/15(土) 19:30~22:00
テーマ
・Fun! 図画工作
講師 横浜市立南太田小学校
永縄 啓太先生
(前 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 教諭)
永縄先生のお話は,とても刺激的でしたね。失礼な言い方になって申し訳ありませんが,
永縄先生が附属横浜小学校で,そして公立の小学校へ戻られてからも教師として素晴ら
しい成長をされていることがわかり,感動しました。これは「誠実に子どもに寄り添い,
見取ろう」とする教育の原点と,「学び続ける」という教師の責務を体現されている
永縄先生の人間性とプロ意識の高さの賜だと思います。
見習ねば・・・と強く思わされました。
参加者からのコメント
・本日も貴重な機会をありがとうございました。自分は若いころは教科書に載っている
からその単元をする,評価・評定もいい加減な教師でした。今は,その単元を通して
どんな力を付けてほしいのか,そのためにどんな導入で,どんな声をかけて…と考え
るようにはなりましたが,永縄先生のお話を聞き,まだまだだなあと痛感しました。
○協働的な学びが生まれるような動線を考える
○その子の前の単元での様子を踏まえて価値付ける
○子どもの心が動く導入
○日常生活の中にアートを見つけ教材開発をする
○子どもが自己発見する瞬間を見取る
○子どもと一緒に考える
○子どもが自己開示しやすい手立て
等々,たくさんの学びがありました。あまり体調がよくなくて,欠席しようかとも
思っていましたが,参加して本当によかったです。図工だけでなく,自分自身の
「子どもを見る目」を見つめ直す契機にしたいと思います。
・足立先生,今回もこのような学びの場をいただきありがとうございました。
足立先生が縁を大事にされているからこその機会,出会いだったと思います。
永縄先生のお話の中で印象的だった言葉は,「作品は自分そのもの」という言葉です。
私も,学校は自分みつけ,自分づくりの場だと思っています。様々な出会いや,経験を
通して自己を作り上げていく。同時に,回りでつり上げられている異なる他者を認め
尊重し,影響し合いながら成長していく。その一端が,作品という物に具現化されて
いるのだと,作品の見方が変わりました。
「創作の終わり」について質問させていただきました。お話を伺いながら,当時も今も,
こんな表現ができるようになってほしいという願いがでてしまい,自分を押し付けて
しまっているところがあるなと反省していました。これは図工に限らないなと思います。
しっかりと準備し,考えれば考えるほど願いが強くなり,押し付けてしまう自分がいま
す。教材研究の際に,何をしっかり考えるべきなのか。図画工作科では「子が自己開示
できるように/自己開示した姿をどのように見取り,どう関わっていくか」そこを考える
と良いと学びました。1人1人違うちのだから,ゴールや向かい方もちがう。教師の
準備したゴールがすべてではない。その子の現在地を大事にして,個別最適化された学習
を提供していきたいと思えました。
図画工作科の実践を通して,教育観,学級経営の視点,自分らしさの磨き方など自分なり
に色々学ぶことができました。私も,自分の柱を見付け,永縄先生のような魅力的な教師,
人間になっていきたいと思えました。お忙しい中,私たちのためにお話を考えてくださっ
た,永縄先生に改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
・今日もたくさんの学びをさせていただき,ありがとうございました。永縄先生のお話を
お聞きする中で,特に2つのことが心に残りました。
1つ目は,図画工作科が本当に子どもたちが自分のものを表現する時間になっているのか
ということです。永縄先生のお話にもあっように「白いところいっぱいあるよ」という
言葉をよく子どもたちの作品を見て言ってしまっているなと反省しました。子どもたちに
ああしなさいこうしなさいということよりも,なぜこのような絵を書いたり作品を作った
りしたのかを考える教師になっていきたいと感じました。
2つ目は,どこの段階の作品を見取るのかということです。今まで僕は完成したものを
見取ることが多かったです。そうすると,なぜこのような作品になったのかが見えず,
作品主義になりがちでした。しかし,今回のお話をお聞きする中で,作業をしている時に
いかに見取るのかが勝負だと感じました。評価を残すタイミングを学ばせていただきま
した。図画工作科だけでなく,他教科でも大切なものを学ばせていただきました。
・足立先生、本日も素敵な会に参加させていただきありがとうございました。ずっとわくわく
してお話を聞かせていただきました。わたしはお話の中で「学校は子供の遊びにあふれて
いる」という言葉が心に残りました。お話をされている永縄先生は終始楽しそうで、キラキラ
されていて、子どもたちと一緒に楽しんで授業を作っておられるということがひしひしと
伝わってきました。だから、子どもたちも楽しんで自由に自分の思いを出せるのだろうなと
思いました。図画工作科はもちろん、どの学習でも一緒に分からないことを悩んだり、喜ん
だりしながら、一緒に思いきり楽しみたいと思います。
また、図画工作科のつくる過程の中で、一人一人の困りや素敵なところを写真や動画などで
記録し、しっかり伝えていくことを大切にしたいと思います。永縄先生、本当にありがとう
ございました。1/29の外舘先生のオンラインセミナーっもぜひお聞きしたいです。
・今日もありがとうございました。図工はとても個性が出るので子どもの作品を見て面白いと
思う教科でした。永縄先生の話をお聞きして、場の設定や声掛け一つ一つにも大切な意味が
あることを知りました。今日見せていただいた実践を見るととても子どもたちが楽しそうで
私も一緒に授業を受けてみたいなと感じました。この作品いいねとみんなに見せ時、その
作品を真似して自分の本当に表したいことができていない児童がいるのですが、その時
どのように対応したらよいか教えて頂きたいです。
・昨日はありがとうございました。話していただいた内容をもとにして、自分なりに言葉や
実践について振り返ることが出来ました。テーマは図工でしたが、(中学校の)社会科や
学級経営に活かせそうなこともたくさんありました。聞いていて心に残ったことやそこから
考えてみたことを以下にまとめました。
そもそも社会科って何か、自分にとって社会科とは、子どもにとって社会科とは
→社会について学べる教科、社会に出て役立ち生きる教科、よりよい社会をつくる上で
必要な人材を育成する教科、すべての教科と関連する教科、知識が多い教科、常に
更新し続ける教科、抽象的な概念を獲得する教科
→得点を取れるから楽しい教科、世の中が見えてくる教科、一番学ぶべき教科
→暗記教科、資料から読み取る教科、テーマについて話し合う教科
学ぶ意味や学ぶことで自分の成長とどうつながるのか
→自己実現のため 自分の可能性を広げる、力を伸ばす、目標を実現する
→社会に役立つ人になるため 人は社会的な存在であるため学び所属する社会で活躍する
教科書への落書き→美術の時間であれば一つの作品になる
図工とは言語と違う形で表現できる教科、子どもの姿がそのまま表れてくれる教科
自分が動いてみてわかると教師が教えるより身に付く
→大事なことは自分で気づいて発見できたこと→深く心に残ったこと
図工?で子どもが授業の最後で一番伸びているのかはわからない
→自分が残したいものを残していくことが大切
場の設定→子どもの動線を考える
材料の精選→大きさ、造形 発話→共感+共に考える
「これでいいですか?」だけは聞きたくない
→ゴールは子どもが決めるのであって、教師を満足させることではない
評価基準があれば、それにのっとっているか聞いてくるのは仕方ないけど…
起こっている状況に対して肯定的に見る
→どこに子どもの学びの場面が転がっているか分からないから常に好奇心を持ち向き合う
同じことでも見方を変えれば違う世界が広がっていく
→整然と並ぶ花、実は背丈が違う花、つぼみと花、虫の存在など
興味をもってもらうために
→①鏡を開いた状態で教師が見せる ②各机上に鏡を置いて静かに画用紙を渡す
評価…その子の今の姿を知る 評定…数値化したもの
作品はその子そのものである
これを見ては作品だけでなく、その子を見ることも大切
→それだけ子どもの様子を見ておくことが必要である
学校は自己発見と自己開示の場では!?
→学校で出会う様々なことから自分が感じ成長していく
ロイロで無記名にすることで、自分の意見が共有しやすい
→人ではなく、意見に対しての興味や関心につながる 協働的な学びにつながっていく
ロイロで意見提出をするときに色分けして自分の表現をする
→赤は自信あり、青は自信なし、緑はその間
協働的な学びを促進するために、個人に応じた手だてをうつこと
このためには、前提としてどのような課題に取り組んでいるかを明確化する必要がある
個人に応じた手だてをうつことと支援はどう違うのか
町中を歩く中で、素材を見つけて学習材にしていくガッツ
同じことをやっていく中で、それぞれの追究方法を保障していく。ただし、個人だけで
できることに限りがあるので、協働的な学びが必要になってくる。そして、他者と協力
をしてより個の学びを深めていく。
・昨日も貴重なお時間をありがとうございました。私はこれまで、図画工作科においては
教科書に載っている教材しか扱ったことがありません。そこで今回、永縄先生のお話を
お聞きし、大人でもワクワクするような教材開発をされていることを知り、永縄学級の
子どもたちが羨ましく思った半面、私も頑張ってみよう!と刺激をいただきました。
日々、題材にできそうな場面は多々あることに気づいたので、もっと周りにアンテナを
張り、自分も子どもたちも楽しめる授業づくりができるように頑張っていきたいと思い
ます。また、図画工作科の時間には、ついつい「もう少しこうしてみたら?」と声を
かけてしまうときもありますが、「作品はその子そのもの」という言葉を大切に、支援
していきたいと思います。
・昨日はありがとうございました。私は子どものときに、自由に表現する図画工作の
授業が難しいと思っていました。なので昨日、永縄先生のお話を聞き、身近なもの
から題材にされ、実践されていることで子どもたちはこんなところにもおもしろい表現
があることに気づくのだと思います。そして、イメージを大人以上に膨らませ、表現
することができるのだと思いました。来週から版画の単元に入るので、いろいろな形に
着目しながら頑張りたいと思います。図画工作科がとても楽しみになってきました。
そして,なんとありがたいことに永縄先生からもメールをいただきました!
・本日は、かのような舞台を用意下さり、ありがとうございました。
また、「自由に己を語ってよし」との言葉、ありがとうございました。
その言葉があったことで、自分が、これまで大切にしてきたこと、「今」、大切にして
きたことについて心おきなく、語ることが、出来ました。
語る、ということは、自己発見であり自己開示でした。
今日、このような時間を過ごさせて、頂けましたこと、感謝しきりです。
足立先生にお会い出来たことに、感謝、感謝、感謝です!
また、私が今日のように、思うがまま好きに語れたのは、私の話に耳を傾けてくださった
「誠実なる」聴き手がいたからに他なりません。
あすなろ会のみなさん、参加者に感謝です。



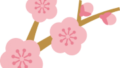
コメント