2/19(土) 19:00~22:00
テーマ
・ 新学習指導要領における「体育科の見方・考え方」について
講師 鎌倉市教育委員会指導主事
濱地 優先生
(前 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 教諭)
参加者からのコメント
・今回もすごく興味深く,面白い内容で,自分も挑戦したくなりました。
<特に心に残ったこと>
○遊び/アフォーダンス:環境が行動を引き起こしている「思わずしてしまう
環境・活動設定」…「主体的」に学べるようにするためのヒントを頂きました。
○できるかな?できそうかも!?と「できる・できないの間(あいだ)」を意識
して授業デザイン…自分の授業には間がない時が多いとふり返りました。子の
間を意識するとワクワクする子が増えそうなので,自分も単元構想の時に意識
したいと思います。
○受け手の価値づけ…強く意識して実践できていたかと思うと否。意識しなおし
ます。
○単元名・テーマに単元の特性を埋め込む…単に楽しそうな単元名をつけていた
のではないことが分かりました。その特性(その運動の固有の面白さ)を意識
することは,何をどのように学び,どんな力が身に着くようにしたいのかと
考えることにもなると思いました。
○共生・仲間づくり…心と体を一体と捉え「からだ」。「からだ」が動き出すには,
心も体もほかほかにしないといけない。
これだけ見ると,体育科に限ることではないですよね。体育を通して子どもたちを
どのように育てるのかを学ぶことができた3時間でした。お忙しい中お話頂いた,
濱地先生に感謝いたしますとともに,今回も繋いでくださった足立先生にも感謝
いたします。
全国的に外国語,理科,算数,体育が教科担任制になっていきそうな流れがあります。
小学校教員をする上でさみしく悲しく思います。なぜ,教科担任になるのか理由を
見ると,「授業の質の向上・学習内容の理解度,定着度の向上」「円滑な小中接続」
「多面的な児童理解」だそうです。良さもあるのかもしれないし,私が古い考えから
抜け出せないだけかもしれません。ですが,体育は,座学ではない場で担任が児童と
心を通わせ,育てられる大事な教科だなと感じているので,担任が担当したいと感じ
ています。
・本日も貴重な機会をありがとうございました。社会も体育も自分でやっていないことの
デメリットの方が大きすぎるなあと改めて感じました。今回の勉強会で一番感じたのは,
体育に限らず自分で単元開発をしていくことの大切さです。人の作った単元計画で授業
をし続けていてはいつまでたっても教師としては半人前。元ネタはあったとしても教師
の「意図」「願い」「ねらい」をもって教材化することが,教師の仕事。先ほどアップ
した総合の授業にしてもそうですが,生みの苦しみがあるからこそその先の喜び(子ど
もの育ち)がある。そんなことを感じた勉強会でした。
・昨日もありがとうございました。前回の勉強会と今回の勉強会で共通しているのは、
環境づくり(学びたくなる環境、仲間づくり、しかけづくり)と教師の練り上げられた
考え方の大切さだと思います。平野(朝久)先生の「はじめに子どもありき」という
本を読んでいるのですが、子どもを能動的な学習者として捉える子どもが観が必要だと
書いておられます。また授業が貧しいことを、子ども達は本当はパンを食べたいのに、
教師が石を与えてかじらせているのと一緒だと表現されています。それに対して、本日
の濱地先生の講演の内容は、子どもがいきいきとする授業となるために考え抜かれて
いると感じました。学習指導要領を自分の言葉で捉えて、授業の中に落とし込んでいく
ことを来年度はさらに意識してやっていきたいです。体育の内容で実技的なところは、
分からない部分も多かったですが、「自分ならどうするかな」や「自分の教科で活かせる
ことはないか」と考えるこの時間が自分の成長につながると考えています。今回の場を
作っていただきありがとうございました。卒業まで残り数日となりましたが、「子どもに
とってどうか」を忘れずに実践を続けていきたいです。
・昨日の勉強会,ありがとうございました。濱地先生のお話をお伺いして今まで自分が体育の
学習について考えるときに大切なことが抜けてしまっていることに気づくことができました。
それは,共生というところと安心というところです。
共生というところは体育の学習をする時にあまり意識できていませんでした。技能のレベル
で分けることに違和感を感じずに,今まで過ごしていたように感じます。どうしたら共に
楽しめるのかを考えることは,子どもたちにとって,そして教師自身にとって必要なこと
だと思います。こちらから一方的に「こういうルールでしましょう」とするのではなく,
子どもたちの知恵も借りながら共に楽しめる体育の学習を創っていきたいと感じました。
そして,安心というところでは,今まで安全には配慮しているつもりでしたが,心理的な
ところで配慮ができていなかったと思います。得点板も「必要だろう」と何気なく使って
いました。なんのために必要なのか一つ一つ見つめ直すことが大切だと感じました。
また,教師は人柄と人格が大切だと勉強会に参加して感じています。私自身まだまだ人間
として未熟なところがたくさんあります。僕の好きな言葉に「我以外皆我師」という言葉が
あります。子どもたち,周りの先生方,保護者など周りの方からたくさん学んでいきたいと
思います。
・途中からでも、参加して本当によかったです!体育の学習では「身体」だけでなく「心」と
「頭」も一体化させることが大切なのだと学びました。友だちと学び、高め合うことの
楽しさを引き出していけるようにしたいと思います。体育の学習に限ったことではありま
せんが、子どもたちの中から「ハテナ」をたくさん出せるようにしたいです。
・昨日もありがとうございました。私自身、体育が大好きなので苦手な子へのアプローチ
を悩んでいましたが、昨日でたくさん学べました。「できる」「かつ」と「できない」
「 まける」 の間があるといいという言葉が印象的でした。今、宝運び鬼をしていて、
私は「なんこでこっちの勝ち」と言っていました。子どもたちの中でリレー選手がいない
から勝てないと勝ち負けにこだわりすぎていた部分があったと反省しています。また、
ウォーミングアップの仕方も悩んでいた所なので勉強になりました。さっそく次の授業
からしてみたいと思います!濱地先生と子どもたちが楽しそうに体育をされている画像を
見られて、子どもは先生の事が大好きだし、体育が大好きなんだなと感じた実践例でした。
質問で、ウォーミングアップはどのくらいがベストなのかなと振り返っていて思いました。
できれば教えていただきたいです。また、たくさん勉強させて下さい。ありがとうござい
ました。

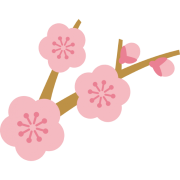


コメント